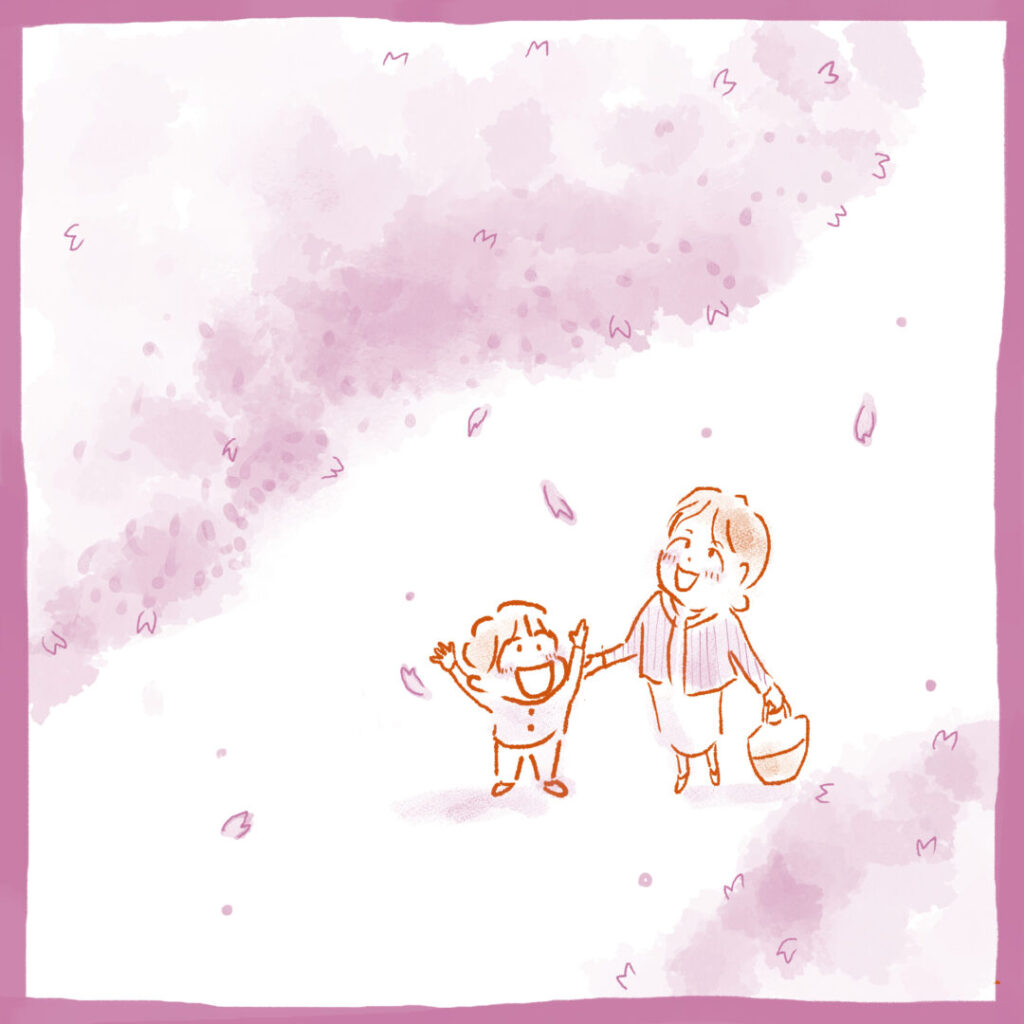終末期の生活環境
要介護5の認定の通知が届いてから、久子さんをめぐる環境が大きく変わろうとしている。
これまでは、要介護2という数字から、まだなんとかなるだろうという、希望的で楽観的な見方がぼくの心の中を広く支配していた。
あおぞらのスタッフやデイサービスの皆さん、訪問看護師さんが良く看てくれている、少々のことは何とかしてくれるだろう、そのような甘えがあった。
ぼくが知らないだけで、あおぞらで暮らす本当の久子さんの姿は、要介護2ではなく、ずいぶん前から今回の数字が示すような姿であったに違いない。
スマホの留守電に担当のケアマネさんから連絡が入っていた。
『担当者会議を開きたいのですが、長男さんにもぜひ参加していただきたいので、日程を調整しませんか』
と落ち着いた優しい声のトーンだった。
その落ち着いた声は、最近抱いていながらも自分で納得させてしまっている、ある不安を想像させた。

あおぞらに込めた想い
あおぞらは、13年前にいただいた奇跡的なご縁と、20年前から抱いている認知症高齢者への思いが、驚くようなベストなタイミングで重なり、ぼく自身が計画をたて、会社に稟議を通して、頭の中で描いていた高齢者の暮らしの場をうまく具現化することができた、サービス付き高齢者向け住宅だ。
認知機能が衰え医療依存度が高く、しかも一人暮らしで近くに身寄りがない、そして少ない年金での生活、このように本当に社会的に弱い環境で暮らす高齢者を、いったいどのように地域が連携してみていけるのだろうか。
この難問を20年前に、訪問診療を中心に活動しているある医師から投げかけられて、ぼくの人生は変わった。
勤めていた会社では介護事業の子会社の社長を拝命し、この難問に挑む環境が整い、社長に就任するとほぼ同時期にあおぞらにチャレンジすることができた。
またプライベートでは、父が、がんの治療を緩和ケアに切り替え、自宅で訪問診療を受けながら、最期を自宅で看取るという経験ができた。
しかしその間、家族の疲労は徐々に蓄積し、久子さんの心と体を蝕み、父が亡くなる前に認知症の症状を発症していた。
父の看病に疲れ、一人暮らしになってしまった久子さんが愛おしいと思う気持ちと、認知症の症状に怒りを隠せないことに対して自責にかられる気持ちとの闘いの中で、生活を見守りながら、10年間久子さんの認知症と向き合ってきた。
このような経験は誰にでもできるわけではない、ぼくの人生は、長いレールが敷かれていて、その上にのっているトロッコのように、自然に流れてある方向に進んでいるように思えてならない。
久子さんのために建てた施設ではないが、あおぞらは、自信をもって自分の親にも入所してほしいと思える施設、サービス付き高齢者向け住宅だった。
しかし、認知症高齢者にとっての現実をよく見ると、サービス付き高齢者向け住宅と、介護付き有料老人ホームや特養(特別養護老人ホーム)との違いが大きく、夜間や早朝の対応の差は歴然としていた。
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が自由な生活を送りながら、近隣の医療機関や訪問看護との連携を密にできるならば、必要な時に必要なだけサービスを受けられるという、理想的な高齢者の生活環境を作ることができると思っていた。
現在、あおぞらでは100歳を超える入居者さんが生活している、そして過去には、家族やあおぞらのスタッフに看取られ最期を迎えた方もいた。
しかし、久子さんのように、認知症の症状が重い高齢者には限界があるのだ、ということを今回、身をもって学んでいる、そしてこの経験はレールの上にのって進んできたトロッコの、必然的な景色なのだろうと感じ始めていた。
長男の選択
4月上旬、狭山に向かった。
さくら並木は薄いピンク色の花が咲きそろい、黒く太い幹の横を通った時、手が届くような高さのところに、小さな細い枝が出ていて、3つか4つほど小さな白い花を咲かせていた。
いつかどこかで同じ景色を見たことがある、長い枝が水平の伸びた大木の、黒い太い幹や、根っこから小さく細い枝が出ていて、その枝に桜の花が3つか4つ咲いていて、とてもけなげでかわいい。
桜が満開になる季節、人生の節々の記憶がよみがえってくる。
保育園のイベント、小学校の入学式、家族での花見、久子さんがどのような気持ちで、仕事や家事の合間に子育てをしていたのか、今となっては聞くことはできなくなったが、アルバムの中の若い久子さんの表情は小柄ながらも明るく、まるで小さなさくらの花のようだ。
久子さんの人生の終末期の生活環境を決める、大事な担当者会議が始まった。
戦前に生まれ、結婚と同時に大家族の面倒を献身的にみてきた母親の、長い波乱の人生、その最期の時期をどのように整えるか、久子さん自身が選択できることではなく、そのキャスティングボードは長男が握っている。