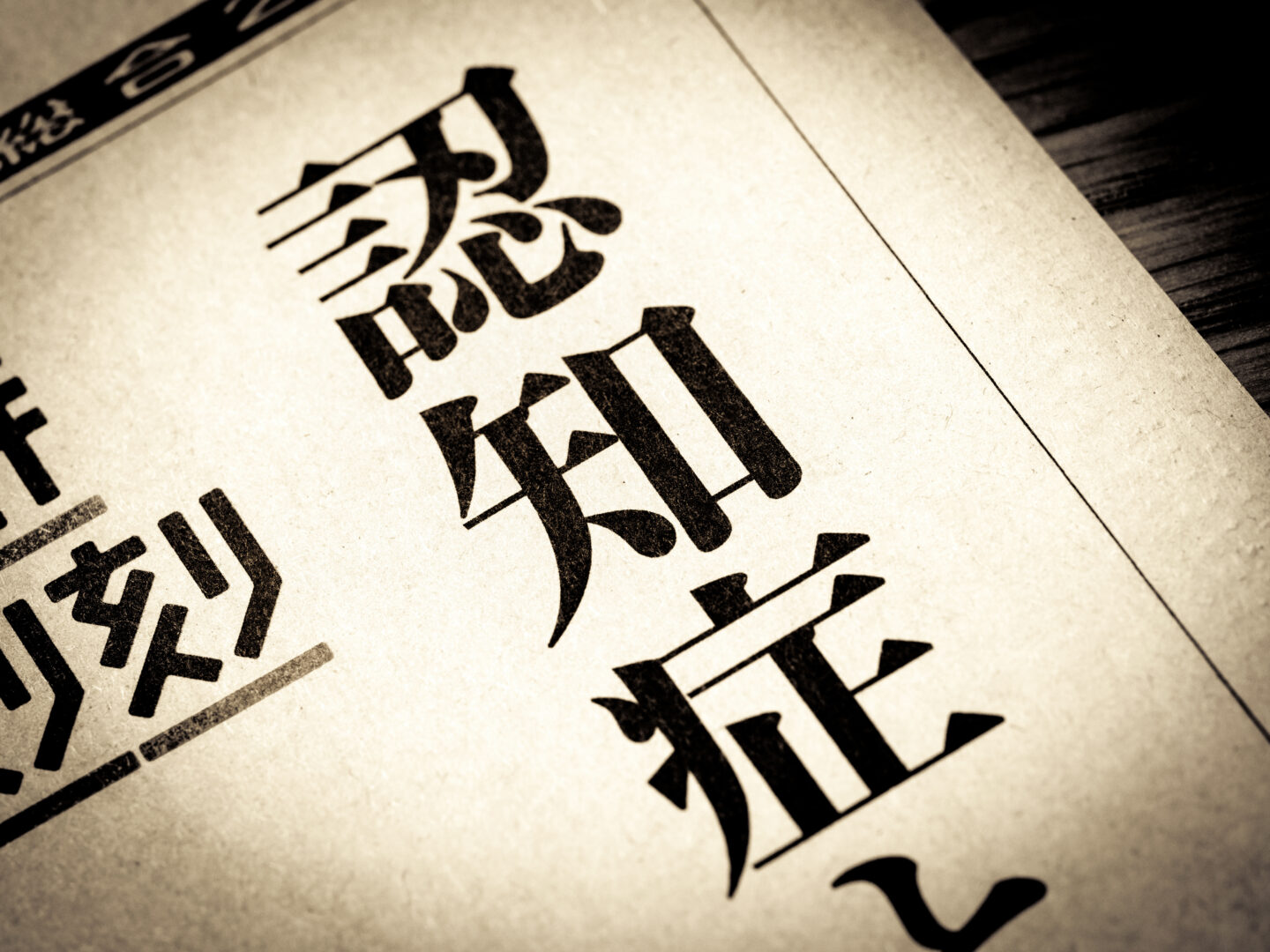2024年1月1日に施行された認知症基本法は、その基本理念として「すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる」と明記しています。この法律に基づき、同年末には第1期の認知症施策推進基本計画も閣議決定されました。
しかし、「全ての認知症の人が、自らの意思によって…できる」という理念には、大きな違和感を覚えます。これは、認知症のある人の権利を強調する表現ですが、現実にはその権利を行使することが難しい方もいます。

近年の高齢者が関わる痛ましい事故や事件の報道を見るたび、この理念と現実との間に大きな隔たりがあるように感じます。
高速道路の逆走、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる大事故、孤立死、特殊詐欺被害、そして火災など、一般の人々を巻き込む事件・事故も後を絶ちません。これらの悲劇を防ぐことと、認知症のある人の「自らの意思」を尊重することは、時にトレードオフの関係にあるのではないでしょうか。
核家族化が進む現代で、本人の意思を優先するあまり、再び家族に介護の負担が集中すれば、政府が掲げる「介護離職ゼロ」の目標も達成が困難になるでしょう。また、住み慣れた家での暮らしを続けることは、事故や事件だけでなく、自然災害の多い日本においては安全上の懸念も伴います。