新たな久子さん
ぼくの中の久子さんは、何かが変わってきた。
これまでは、健康な時の母親としての久子さん、そして認知症を発症してからの久子さん、この二人だった。
まだうまく表現できないが、ぼくの中に新しい久子さんが生まれ始めている。
ただ考えるだけではなく、見えない久子さんの心の中まで想像し、これまであった出来事を思い出しながら、できる限り正確に文字に落とし込んでいる。
ぼくの頭の中に漠然としてあったものを、知らない方が読んでもわかるように書いていく、すると今まで感じていなかった、久子さんの気持ちが見えてくるような気がする。
正直、こんなに母親のことで心の中がざわつくのは、小学生のとき以来だ。
小学生の頃は寂しさで心がざわざわしていた、とにかく母親に会いたかった、母親のことを思いながら過ごす平日、休日の土曜日日曜日がとても待ち遠しかった。
そして今、ぼくは母親の人生を振り返りながら、我が家の歴史を振り返っている。

小学生のころと違って、今は「わくわく」を感じるざわざわ感だ。
亡くなった伯父さん伯母さん、そして父親、おばあちゃん、ひいおばあちゃん、今はもう会えない人たちの顔や言葉だけでなく、におい、音、天気や温度、その時の感情が断片的ではあるが、ぼくの心に強い影響を残したシーンが、「ぼくの久子さん」を通してよみがえってくるのだ。
ノンフィクションだから、どこまで書くべきか迷うことが多いが、何かに引き寄せられるように、まるでレールが引かれて自動運転されているような感覚で執筆している。
我が家の夕飯の準備は10人分が必要だった。
父、子供二人、おばあちゃん、ひいおばあちゃん、父の兄弟の伯父さん伯母さんが4人、そして久子さんの分を入れると合計10人分になり、それを久子さん一人で準備していた。
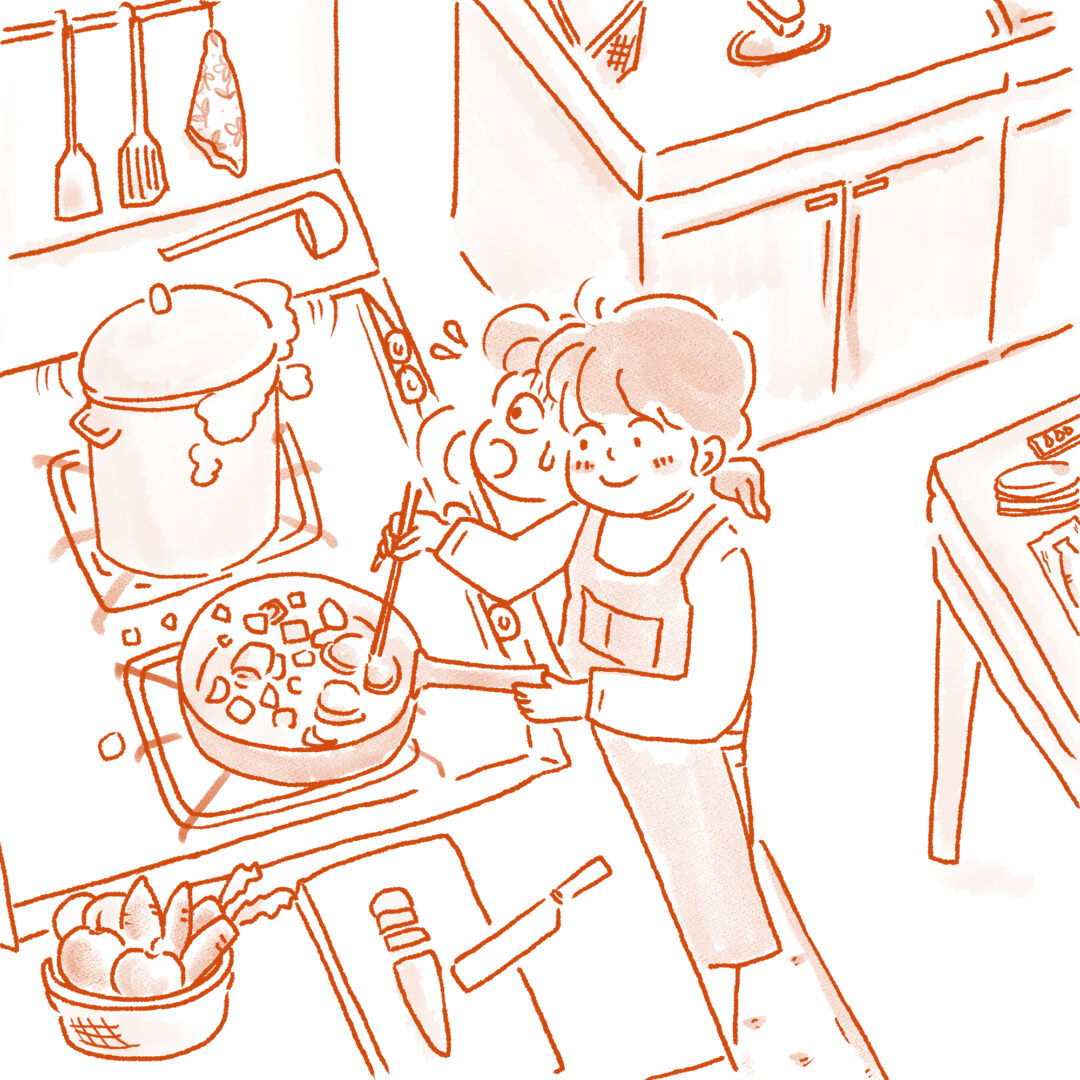
伯父さん伯母さんはまだ学生だったから、朝はお弁当作りもある。
そのすべての買い物も含めた食事の準備をどのようにこなしていたのか、とても想像がつかないが大変だったことはわかる。
だが、物心がついたころから今まで、久子さんから、その大変さについて、嫌だったとか辛かったとか、一切聞いたことがない。
これは父から聞いた話によるぼくの想像で、真実を確かめることはできないが、久子さんは旅館の娘として厳しく育てられていたようで、旅館の仕事を手伝わされた、一度にたくさんの人たちの料理をつくることに慣れていたのではないだろうか。
もう一つ、これはぼくが久子さんを見ていて感じたことだが、久子さんは料理をつくり、人をもてなすことが大好きだ。
どんな理由があるにしても、久子さんはすごい人だ!
これまでは、ただそのことを”知っている”だけだったが、「ぼくの久子さん」を執筆するようになって初めて、久子さんのすごさを、心から感じられるようになった。
もっと久子さんのすごさを見つけたくなった。
これからも、「ぼくの久子さん」を執筆しながら記憶の奥にある風景を思い出し、当時は当たり前だと思っていた久子さんのすごさを存分にほり起こしていきたいと思う。

